今「表現未満、実験室」では、「しえんかいぎ」を5回行なっている。
先日24日に1回目があり、オガ台車でちょっと有名になったおがたくんの「しえんかいぎ」だった。
1月31日は久保田たけしのしえんかいぎ。
その後、2月7日、8日、13日と続き、2月25日は最終の「カンファレンス」。
美術評論家の椹木野衣さん、日常編集家のアサダワタルさん、社会学者の天田城介さんとトークします。
支援会議と言うのは、福祉事業を行っている法人であれば必ずやらなければいけないもので、これで、利用している方々の「支援計画」を作成していく。
レッツでも、アルス・ノヴァという障害福祉サービス事業所を運営していて、その中で年間40人~50人の支援計画を作っている。
支援計画も、支援会議も「できないことができるようになる」あるいは「する」ためのものだと思われているし、または問題解決型。
困った問題が解決するように、どう組み立てていくかと行った会議と計画になる。
でも実際、重度の知的障害のある人たちは、本人が変わったり、いわゆる良くなったりしない。
なかなか変われないから障害者と言われるのであり、普通の人達だってそうだが、他の人がその人の「問題」だと思うことが、その人にとって「問題」だと思っているとは限らない。
ある意味、一方的に社会的な観点から、「問題」だとされてしまうけれど、そこには様々な本人たちの事情だってある。
そうしたことはあまり語られない。
というのも、それは、「本人たちには問題がある」ということが前提だし、「社会の規範に合わすために必要なこと」という条件がつきまとう。
そこで、一度これらを取り払って、「しえん」と言うものを考えてみたいと思った。
やり方は、スタッフがその人の日常を説明し、感じていること、まあ困りごとも含めてプレゼンし、その後、哲学者の西川勝さんにはいっていただいて、「てつがくカフェ」風(レッツではかたりのヴぁ風と言っている)に行っていく。
先日のおがたくんの「しえんかいぎ」は、おがたくんはなかなか時間通りに動けない人で、一番困るのが帰り。お迎えがきているのにまったく帰れないこともしばしば。
また、要求が通らないと「かたまる」。てこでも動かない。で、そのためにスタッフはあの手この手を考え出す。
オガ台車もオガエンジェルもそうした中から生まれたプログラム。
それがアートの人たちにヒットして注目されたりするのだが、その最後の排泄物みたいなものを作品と言われても、私たちにはピンとこない。
むしろ、その過程のほうが、たくさんの試行錯誤があり、スタッフとおがたくんの涙ぐましい、バトルがある。
当日、西川さんから「固まるってどういうこと」という「問」をうけて、皆で考えていたら、実は「かたまる」と考えていた、感じていたのはスタッフで、本人は「かたまった」わけでは実はないのではないだろうか?
この人にはこの作法、方法というように使い分ける術であり、最もおがたくんにとって好都合な条件を引き出す技であるかもしれない。
そういうところは見えてきた時、本当に「ハッ」とした。
「障害者だからできない」「分からない」と思うのはある種思い込みで、彼らは巧妙に我々をコントロールしているのかもしれない。
そう考えた時に「しえんかいぎ」とか、「しえんけいかく」って全く違うものになる。
ここで語られていることは、少なくとも何かができるようになるものではなく、障害のある人とスタッフの間で展開されている色々なやり取りが露呈していく。
それが重厚であればあるほど、その人の生活は豊かになっていくのではないか。
まさに、人と人とが作り出す文化なのではないかと思う。
そして、このやり取りですら、実はすごくクリエイティブで、福祉のお決まりの「支援会議」が、いくらでもクリエイティビティーの発露になれることを物語っている。
クリエイティブとは、そこにクリエイターやアーティストが居ることが必須ではなく、普通の人たちのクリエイティビティーな気持ちさえあればいい。
つまり、何かに囚われたりしない自由な気持ちと雰囲気。
それさえあれば人が自由にな考え方ができる(はず)。
現に、しえんかいぎは一般公開なので、会議に参加してくれた他施設の方々も「うちの施設でもやれるかもしれない」と言ってお帰りになったが、そうなんです!
いろいろな人達が自由になり、クリエイティビティーを高めるのは、特別な力がある人の力技で解決できるものではなく自分たちが内側から変わっていくものだと思う。
だからこそ、福祉事業を行なっている人たちに馴染みのある「支援会議」をちょこっと、アート的に行なうことで、ガラリと変わる。
もちろん、既存のフォーマットにはそれなりの意味があり、それを改良するのは実は難しいことではあると思うけれど、「おもしろい」と思った人たちが最初は真似や遊びでもいいからはじめていくと、何か新しい地平が見えてくるかもしれない。
そんな表現とも言えない、一般の人たちの発揮するクリエイティビティーを、「表現未満、」と位置づけて、発信していきたいと思っている。
このムーブメントが広がっていけば、教育も、政治も、いろいろなところが変わるだろうと夢想しています。
と同時に、文化や芸術、アート様々なシステムを変えて行く力があるのだと信じている。
レッツが他の福祉施設とちょっと感覚が違うのは、アート的なところから始まった施設であるということも大きいが、今いるスタッフを鍛えているのは、明らかに、障害のある人たちだ。
彼らと毎日接することで価値観が変容したり悩んだり、考えたり・・。
そして、最終的には、
何が正しい、正しくないではなく、自分がまずどう感じ、どう考えたか。
そしてどう行動するか。
これって、良くある啓発本やセミナーと全く同じことを言っている。
重度の障害者施設の営みから溢れた言葉は実は社会を変えたい人たちと同じ言葉にもなるし、新しい発想を生みたい人たちとも同じになる。
皮肉のような真実。
重度の障害者たち、可能性あると思いません?
(久保田翠)




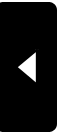

コメント