
スタッフの佐藤です。
「トークイベント担当者は記事を上げるように!!」と、久保田施設長より指令が入ったので、
日にちが空きましたが(スタッフ渡邊くんも記事を上げてくれてましたが)
1月20日(金)に行われた『公開トーク「表現未満、」の姿とともに』
第一回「今の文化政策からみてみた」大澤寅雄さんの記事をUPさせていただきますねっ。
生態系と文化 粒子と波動
前日の夜には「スナックるな」でボロボロとピーナッツの皮をこぼしてはフネフネと酔っ払いだし自分が話したい事しか話さない私スタッフ佐藤の話を温かく聞いていただきまして本当にありがとうございました。
ゆったりと翌日をむかえ、再び実験室に来所し、アルス・ノヴァの利用者さんと過ごす中、「PCにむかってしまうと内に籠ってしまうから」と、憲法の一文を写経しはじめた寅雄さん。横でガムテープやアルファベットを描いている皆さんとの共鳴が印象的でした。
夕刻を迎え、トークが開始されました。
まずは昨晩宿泊されたシェアハウス「のヴぁハウス」の近くにある佐鳴湖を歩いての話をされました。葦が生え沢山の水鳥や魚の居る湖。水辺から林へと続く中には、様々な生き物の生活が連続し関わりあい支え合ってもいる。時には争いながらも共存をしている。そんな生態系の姿が「文化」においてもできたらないいな、と仰っていました。
眼差しをアルス・ノヴァに向けると、ねてる人、はなす人、かいてる人、「いろんな人がいるなぁ」と大澤さん。3Fのスタジオアルスのセッションでは「よくわからないけど、なんか伝わってくるものがあるな。あ、なんだか楽しくなってきた!むむ!壮くんに徐々に伝わってきたか!?おっ!近づいてきたぞっ。」とよくわからないけれど何か伝わり、感じるものがある、と感じた大澤さん。それは「粒子と波動の二重性」で説明できるかもしれない、と。
粒子、粒はひとつふたつと分けることができるが、例えばカレーライスは美味しくても、ジャガイモやニンジン、お米にルーと分けられてしまってもそれぞれが美味しいとも限らない。つまり、理解したとしても美味しくない。
波動、波は全体が揺さぶられて分けることができない、しかし波そのものを止めることもできてしまう。理解できなくとも、なんだか面白いなぁと感じることがある。そんな事を感じていただけました。
様々な条約を通して
トークのお題となった「今の文化政策からみてみた」、しかし実はレッツの活動から「今の文化政策 を みてみた」なのではないか?文化政策のおさらいも込め、(日中に写経した)様々な条約や憲法の条文を見ながら共に考える時間が始まりました。
まずは、ユネスコ「文化的多様性に関する世界宣言」。そこには「共生の方法」という言葉が書かれ「この一文をよくぞ入れてくれた!」と。一方、日本国憲法には「文化とは何か」が明確に定義されていない。基本的人権とは健康で文化的な最低限度の生活であり、「文化」とは美術館やコンサート、または文化芸術のみを指すのでは無く、世界大戦を経て戦争や武力ではないものとして「文化」という言葉が上げられたのではないか、と。犯すことのできない永久の権利として信託されたものであると書かれている。
そして障害者基本法の条文(昭和45年)には、「…全ての国民が障害の有無によって分け隔てられる事無く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」と、ユネスコの文化的多様性に関する世界宣言に有る「共生の方法」に通ずる共生に関する文面が見られる。また、「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」と書かれ経済と文化について共に記述が成されていた。
文化芸術振興基本法には「国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため…必要な施策を講ずるものとする」とある。
問題が生じた時に、条約や憲法にある一文が助けと成りうる事もある。現在の生活における基盤とされ決して甘く見てはならない、と。
…そして、トークは久保田さんを交えトーク形式へと入ってゆきました。
トーク
久保田(以下、久):条約の記述から行政へのアプローチに重要であることを感じた。ここ『「表現未満、」実験室』を目撃する人、関わる人から何かが生まれていくのを期待している。障害のある人の熱意から様々な事をやってきた。制度として実現する為のアプローチ、作戦会議第一回として、今日。
大澤(以下、大):レッツは「やりたくなっちゃう」熱意が豊かな場。波を持っている。しかし、制度としてしまうと、それは起きづらくならないだろうか?また、思うものと違う形が生まれていってしまう事も。
久:厚労省の方達が具体的な作品を制作しない「レッツ」を目撃し、こういったものが生まれるとは!と喜び驚いていた。
大:レッツのような活動が制度として必要かは解らない。そして、障害者アートの推進を法案においても見られる今、具体的に障害者アートを明記する事にちょっと疑問も感じている。アーティストにおいても食えるに保障が無い中、何を持って制度化するにあたるのか、と考えると、それは人権故にと感じる。
久:レッツは文化事業から入ってきて今福祉をやっている。優れていなくとも誰もが文化芸術を享受する事ができると思っている。福祉はマニュアルが先行しがち、そこにアート・文化が入って初めて効果が見られると感じる。
大:共感します。文化芸術そのものが役に立つというよりも、他のものと合わさることで効果や価値が現れる。しかし一方、文化財が観光産業の為に有るように見え、文化芸術を活用するが故に固有の価値を尊重しなくなってしまってもいる。
久:アート、文化はそもそも役に立たない金にならないけれども支援され守られていくものでもあると感じる。
会場に来場された皆さんからも意見や質問が上がった。ある男性は、行政と民間の間の溝について語る。課題は浮き彫りなのだが現実が伴わない。スパイスとしてレッツが有ると話してくれました。
生態系の話から「ビオトープ」という言葉が上がった。自身が居心地よくいられる場(ビオトープ)が社会に必要で、ここ『「表現未満、」実験室』もビオトープと呼べる。こういった場がより拡がっていかないか、そんな話が上がりました。そして、ビオトープから飛び地を創る話、ビオトープは時としてユートピアとして見られてしまいかねない話などが上がりました。

大澤寅雄
㈱ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室准主任研究員
1970年生まれ。2003年、文化庁新進芸術家海外留学制度により、アメリカ・シアトル近郊で劇場運営の研修を行う。
帰国後、NPO法人STスポット横浜の理事および事務局長、東京大学文化資源学公開講座「市民社会再生」運営委員を経て現職。
『「表現未満、」実験室』
http://cslets.net/hotnews/news-736
記述:佐藤啓太





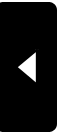

コメント